|
ギー(4版)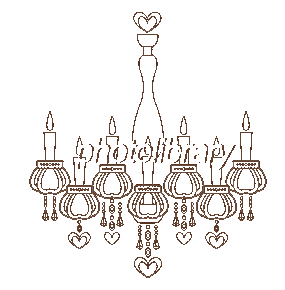
1
ギーのことだ。
ぴかぴかに光ってる通りをぬけて、薄暗くもない空気がちょとつめたい感じの帰り道に、チョビは、急に、あこれはギーだな、と思ったのだ。
たとえば、心細くてしかたのない日があったとする。大切な人や大事だと思うひとがそばにいてくれて、みんなが笑ってくれて、自分もその中で気のきいた冗談の一つも言えるような場所でも、心細くてどうしようもないときがあるとする。そうして、誰も見ていないかえりみち、その誰もいないのに安心して、そっとため息をもらすのだ。このままじゃいけないわけでもないし、考えるほどの余裕もない。
チョビは今じぶんがそんなかんじだとは分からなかったけれど、そういうきもちをちゃんと言葉にできないぶん、帰り道路地のふうけいを見る、左右にごみばこが並んでいて、そのわきで歯をみがいて口をゆすいでいるうつくしいお嬢さんとかのいる、まざったような透き通ったような空気を見ていたら、あこれはギーだな、と思ったのだ。
いつも機嫌がいいわけはない、気持ちはすぐにふさぎこんでしまうというか、ちいさな、穴のようなものがつぶれてしまう。そうするとその部分は結構愚鈍になってしまいわからない。
チョビは、そういうふうなことを言葉にはできないけれど、帰り道にいろいろかがやくものや、きらめくものを見ながら、ほんとうは、あ、これはギーだなとおもう。そうすると、かっこうのいい帽子とか、たくさんの飾りのついたドレスをみていても、瞳はギーをみている、なんて事になる。
それで、しごとのかえりともだちはとなりでそういうチョビを見ていた。帰り道、いつもおおくともだちにしゃべるチョビが何も言わないでいたので、そのかわり、ともだちは少しチョビにしゃべりだすのだけど、返事がないので、ともだちはこりゃだめだなと思う。チョビのともだちはくちをむすんでそのまま前をむく。でもこのチョビの状態はいつもと同じような、いつもよりはひどかない事だ、とともだちは思った。
チョビとチョビのともだちは同じ仕事をしている。
その日のふたりの仕事はとても少なかった。チョビはまた短いズボンをはいていって店の主人に怒られていた。短いズボンをはいてくるなといくらいったらわかるのだと怒鳴られた。今日のは熱をいれたもので、店の主人は二度、三度となく、机をドンとたたいた。そのたびに、チョビはふつうの顔をした。
いつもと同じ、青い生地のおとなしいスカートをはいていたともだちはいくら怒られても同じことをするチョビを店じまいのほうきをかけながらこれまたいつものように脇のほうでみていた。すこし肩をすくめる合図。いつもと同じ、気にかけないふうで、直立したままほうきをかけているともだちの横を通り過ぎるチョビ。いつになっても仕事を覚えようとしないチョビ、要領がわるくて主人をつかれはてさせているチョビ。
ばかなチョビ。仕事だけじゃない、いつだってどうしようもないいろいろなことをする。のろまで、変なところだけみょうにはやい。つねにおうせいに動くチョビ。そのいろいろなこと、無駄なことはきっと誰のやくにもたたないのだ。しょうひばかりして生産せいがまるでない。
チョビのともだちはそういうチョビのせいしつをよく知っている。いつまでたっても仕事をおぼえない、ばかでだめなチョビ。遊ぶ以外にろくなことをしない。だから、ともだちの賞賛は勝ち得ない。
チョビにしてみれば、おこられること、そのたいろいろなことはすぐ忘れがちなことだった。だから、ばかだといわれてもしかたがないところがあった。馬鹿という本当のいみも、よく分からないところがあった。それだけとあるものごとを信用をしているところがあった。
いろいろなことはすぐわすれてしまう。勝手にわすれてしまうのだから、とどめようもないのだ。
チョビはその日ギーを思いひとりはないきを荒くしていた。ともだちの視線はそういうチョビを素通りして、向こうの家の軒下でかみのぐあいを見る犬をつれたおんなのひとにむく。「ギーか、ギーだね」とともだちはひとりごちた。それから主人に頼まれた明日の包み紙をよいしょと持ち直す。これがぬれてはたいへんだ。
なにもひいきをするわけではないが、しかしだれがどう見たってチョビのともだちはチョビとくらべいつも申し分ないはたらきをしていた。それにくらべれば、チョビのはたらきぶりは仕事といえるしろものではなかった。チョビはまるきりやくにたたないのだ。まるでやくにたたないために仕事に来ているよう。誰が見たってそう見るだろう。チョビにやる給料の半分はともだちがかせいでいたのだと。チョビはどじをふんでばかりで、ほんとうにろくなことをしなかった。めったに商売にこうけんすることはなかった。チョビは本当に仕事ができなかった。
チョビは本当にだめなやつだった。
主人はそこでともだちとチョビを一緒に働かせることにしたのだ。ともだちとなら、と主人はおもった。あのともだちとならばチョビも誰にもめいわくをかけず、よい働きをするだろう。雇い主としては解雇する以外の、とうぜんといえるしょちだ。ともだちはチョビの紹介で仕事にはいったわけだし、なかよしだし、一緒にはたらくということに不自然もなかった。だまされたかんじもない。あさはかだという実感もない。はじめから、あきらめているのだ。
そのように怒られてもへこたれないチョビ。なにをやっても、駄目なチョビ。
「ねえ、あんた、またやったの?」
「またやっちゃった。またやっちゃったよ。」
くろいかばんを持ったチョビがなんでもないふうに包み紙をもったともだちのほうに答えた。誰でもひとめでわかる。くろいかばんをもった、派手なかっこうをしたのがチョビで、背の高い、地味なかっこうをした女の子が、そのチョビのともだちだ。
「あんたばかねえ」
ともだちはくつをけってなおした。それから口をとがらせて、通りで下をむく。ともだちはさんしゅうかんまえからできていた、ほっぺたのできものをゆびでさわった。チョビは口をいちもんじにしていて、ともだたちはチョビ脇の頬にちいさなむしがとまっているのをみつけた。
「あんた、ばかねえ。チョビ。あんたみたいのはいっぺんのうてんをうすでひいて、死んでしまえばいいのよ・・・・グシグシ」
「へへ。そしたらなおるかな」
「なおるよ」
街のショウウインドウを眺めるのがチョビの楽しみだった。少しはきにすればいいのに。ともだちは思った。少しは気にすればいいのに。いつでも、どこでも自分は怒られていること。少しは傷つけばいいのに。みんなに笑われて、ばかといわれること。なんでもわすれるくせ。少しはかんがえればいいのに、そのスカートはたいしてかわいくないんだってこと。少しはかんがえればいいのに、そのスカートをはいてくることでいくらの得があって、どれだけそんがあるかってことを。
少しは考えたらいい。
「へへへ、あの服きれいだな」
そうやってくちを舐めるチョビには、わるびれた様子がない。今度はまたべつの店のまえでじっとしている。たまにガラスにおでこをごつん、とぶつける。よく磨かれているからだ。それでわらう。おかしくもないどじぶりだ。ガラスには汗だかお粉だかがこびりついてしまいともだちがそれを服のそでできれいにふいた。ふいたさきには、さっきまでチョビが見ていた商品らが飾られている。
そうやってうろちょろして、変な化粧をしてきて、つんとすましたようにして表通りを歩いているとき、ともだちは上目遣いになって口もゆるみがちになってしまってチョビのうしろをズルズルひっぱられて通りを歩いているとき、チョビの肩にはきずの入ったバッグをかけていて、それをブンとまわした拍子にあたまにぶつかったとき、チョビは、あ、こりゃギーだ、と思っていたのだった。
チョビがいくら派手にしていて、いくらばかでも、なにかがこころぼそくなっていたのかもしれない。でも言葉にできないぶん、チョビにはそれはどうなのかめいかくに分からないけれど、そのようにむぼうびで、誰も相手にしてもらえないときのチョビはどうもかわいい男の子みたいだと、ともだちは考えているふしがあった。
ともだちも、そういうときのチョビはせつないし、大切だなと感じる。ともだちはそういう、男の子のようになったチョビを、かわいいという気持ちになることがたまにでもあるので、チョビのことをてっていてきには憎めないでいた。
そんなことよりもなによりもまず、ともだちはいつどんなときもチョビのともだちであるときめていた。それは損得のもんだいではない。ふたりはだいの親友であると、二人のどちらかでも親しい人ならばそう言うだろう。チョビだってかるぐちしかたたかないけれど誰よりもともだちを頼りにしていたし、それはほんとうのことだった。
その証拠になるかわからないけれども、チョビはともだちがいないとすぐこころがだめになるように体を売ったりする。すぐに悪い薬をやったり、熱い火のかたまりを自分の手にあててみたり、すぐ体をいためつけるようなことを平気でする。ものをぬすむことがある、ときには自分だけでなく人をいためつけるようなことにもなりかねない。そういったことが悪いことで、悪いということがどんなことで、邪悪というものがどういうそんざいか、チョビにはわからない。ばかだからわからないのだ。
チョビにはとても優しい親がいてとても優しい兄弟がいて、あたたかい、とても優しい家庭がある。でもチョビは自分にとって、為にならないことばかりするのをいつまでたってもやめない。ちょっとめをはなすとすぐそうだ。きっとばかだからだとともだちはおもう。ばかだからだ。神さまを信じないで、ばちあたりで、あやまりもしない。ともだちはそれがいつも我慢ならなかった。おそらくそれはばかだからだ。神さまのことがまだもっと好きだったころになら、きっと毎日ともだちはチョビのおこないを見てはぎしりをしただろう。とても大きくはぎしりをしただろう。でも今はしない。
今度の仕事だって、と、ともだちはおもった、今度の仕事だって、からだを売るような仕事だとおもったのだ。チョビはいつも平気な顔をする。いつまでたったって、うたがうことをしらないのだ。そういうときは、すこしだけ、てんしににている。
でも、例えば、色のはでなわけ知りがおの奴の話をきいたりして、あらそう、なんていって、知ったふうなそぶりをみせてばかなことをたくさんするチョビのこと。それでも、ある日には、だまされたりする涙にくれて、かみさま、本当にほしいものはなぜ手にはいらないのですか?なんて恥ずかしいことを言ってそういう時だけ泣きながら神さまにすがって祈り願い事をして地に手をついて自分についてあやまったりする。
かみさま、本当に、ほしいものはなぜ手に入らないのですか。
ともだちはそういうセリフのことを考えるとあしの裏がじりじりする。おまけにがまんならなくなって、その場にいなくなりたくなるのだ。くつうのあまり笑い出したくなる。笑ったまま通りを横断してそのまま裏通りへと消えたくなる。
そういう言い回しがあること、あってはならないことをともだちはよくよく考え、よくよく考えたそのことがまた苦痛になって、くつうがくつうを呼び寄せ、足のうらがすこしこげついたかんじでじりじりする。きっとそれは、ともだちのライフスタイルなどにかかわる重要なぶぶんだ。わたしはチョビではない、そんなことはするべきではない、したくはない、何というか、ぜいたくだ。さらに、そのぎもんはチョビにも及ぶ。できれば禁じたい。でも、そういうことだって、もうめったなことでは言わない。
どうせ表面的なことだし、言う機会がないのだ。
仕事がおわり、ふたりはとある交差点で別々の方角へむかってかえってゆく。ともだちは家にかえって部屋のそうじをするつもり。チョビは、これからひとばんじゅうかかってギーのこと、それにまつわる様々なことを思いだし、考えなければいけない。チョビはそれを平気でやってのける。そういうチョビのことに、ともだちはじつはかんがえがおよばない。チョビが一人でいるときの、そのかんがえや、思い出にたいして、ともだちには考えがおよばない。いつもどおり、チョビはだめなんだと思うだけ。しかし、チョビは、これはギーだとかんがえた。このちがいは、ふたりに、どういうわけかおもくのしかかってくる。
そうしてよるはふけてゆく。
2
ギーのことを話すまえにふたりのことをすこし。
ふたりの仕事は包み紙をアパートとかマンションとかに行って届けることだけだ。一見してみるととても簡単な仕事だ。時間もあまり急がないし、歩いてできる仕事。簡単なようだが、チョビにはむつかしかった。チョビにぴったりだぴったりカンタン、なんてことはないからだ。ともだちはいう。
「このあいだはぜひ持たせてくれというから、しかたなく持たせたたまごを、よそんちのへいにぶっつけて全部割ってしまった。私の顔は青くなり、チョビの顔は青くなり。とにかく行ってみると届けなければならない相手が優しいおばあちゃんだったからよかったけれど(チョビはぼろぼろに泣いて謝って(わざとではない)、それで結局おばあちゃんにお茶に呼ばれて笑いがおでにじかんもあぶらをうったのだ)、そのおばあちゃんの、新鮮なたまごを食べることがたのしみだというその言葉にいつわりはなかったし、またそれでもかまわないんだよ、というおばあちゃんの言葉も、また嘘じゃあなかった。
わたしが店主にそのことを言うと、チョビにたまごを渡すなんてふちゅういだ、とわたしがさとされた。これからはよくよく注意するべきだと。さとされたのはわたしで、チョビではなかった。」
でもときどきは危ない仕事もある。一度にたくさんのひとや、思い出をもこなごなにする、ばくだんを投げ込むような仕事もある。そういうときは二人で黒い服を着る。マジョのようなかっこをして、仕事にとりかかるのだ。ふたりでわざとめだつように黒い服を着て、その家その場所へばくだんを投げ込むのだ。
ともだちははじめは泣きそうなぐらい怖くて、いやだったけれど、がまんをした。これでへこたれてはマズいとおもった。ほかにこれといって仕事がなかったし、どんな仕事にもたいへんな局面はある、こんなことでへこたれると、誰かに見放されるようなきがしたのだ。
それでもしかし、泣きそうなぐらいに恐ろしくて、恐ろしさで足がガクガクしてどうしょもならないとき、そういうときは、そのとおりどうすることもできないのだが、そういうときともだちはチョビにすがって、チョビはこしがたたないようでともだちによりかかって、二人で泣く。ひとがしぬのだ。お互いがお互いに抱き合って足をがたがたふるわせる。お互いがお互いの目を見て、それが自分ならどうだろう、と思う。そのときのふたりは、いくらふだんしゃれようとしていても、なさけない顔をしてこしがたたなくなっている。お互いがお互いのなさけない顔をみて、ひとがしぬのだ、それが、もし自分ならどうだろう、と思う。とたんに、その人のことが大切な気持ちになる。それで、軽くだけどお互いがお互いの口をつける。
ひとびとは、それを見てうつくしいといったり、感心だと言うことがある。よくよくこころえるべきだ。そして、仕事をやりとげたあとの感情も、これまた、いいつくせない。
でもだんたんとそういうこともなれていく。
ばくだんを投げ込むといっても、それが彼女らの仕事なので、誰もが許してくれた。仕事をしているふたりには、みなやさしかった。仕事をさえしていれば、わるくいうひとは極端にすくなかった。「僕も仕事をしてるんだ」なんて、声をかける若いアニキもいる。仕事をしているひとにはみなやさしい。食べるためににわとりを殺すのと同じ、どこかで誰かが助かる立派なことだった。みんなそれを知っている。仕事とはかみさまが人間に与えたみわざだ。みなそれを知っている。ばくだんをなげこんで、かなしいのは自分だけだった。それはひとりで、あるいはこのものたちのように処理すればよい。どこかで、だれかが、困っていて、それがたすかっている。何でもそうだがそのうちなれる。にげるわけではないけれど、体をうるよりはましだ。
体をうることはなによりもつらいことだった。自分のものだと思ったものが、他人のものになってしまう。ごうよくにうまれた人には耐えられないものだった。そういうかんがえのもとで、ふたりはしごとをしている。
そういった仕事をしている最たるひとが、ギーだった。
だからチョビは、ほんのすこしだけれど、ギーと同じ土を踏んでいると思うときがある。
3
たまのやすみには、二人は公園へでかけることもある。でもほんとうにたまに。チョビは料理がまったくできないので、かわりにともだちがサンドイッチとかそのたのもろもろをつくってでかけにゆくときもある。
公園にきたっておもしろいことなんてなにもない、としとったチョビはそう言うだろう。チョビはふけた。昔はそうじゃなかった。でも口に出すことなんて、どうせたいしたことじゃない。昔もいまも、こころのなかはがらんどうで、だまっていた。
ふたりの街の公園はさっぷうけいだ。グラウンドだけが広い。風がピュルピュルそこで円をえがいてダンスしているみたいだ。チョビは今日もうそのクルクルをにじゅうごかいも見た。ともだちが用意しておいたバスケットをあけて、一つ目のにんじんいりのパンを少しかじる。
チョビはあしをくんで、もの思いにふけっている。ときどきは好きな男の子の話をするときがある。そのむかしはそういう男の子のことをダーリンと呼んでいた。そう呼んで、その人についていろいろなことをはなして、やがて夕方になった。いまでもそのひとたちのことをダーリンと言うこともある。それはもうほんきではない、じょうだんまじりの呼び方でのことだけれど。
「ねえ、サ」
「なにさ、・・・チョビ」
「あんだかわかんないけどさ、あのローラースケートしている少年、きれいだね。きれいだとおもわない?」
「そう?私はそうは思わないよ」
「そりゃ、あんた目がくさってんだ。サ。いつも思うんだけどさ、あんたものをうつくしいだとかきれいだって思うことないんじゃないの。ほんとうに。サ」
「たしかにあんたほどはないね。・・・チョビ。」
公園の外のアスファルト道路で、ローラースケートをしていた少年はころんで、それを笑ったゴムボール持った少年を追いかけて、公園に入ってきたところで、少年はもう一度ころんで、ひざをすりむいた。
一度にたくさんの痛みをうけて少年はうずくまった。
「ああ」
それをみて声をだしたのは二人ともどうじだった。
「どじだな。ちを出してる」
「そんなこと言ってないで、手をかしてあげなきゃ」
「大丈夫だよ。どうせ死に至るような傷じゃないじゃない。死にはしないのだ。」
「でもだって、泣いてるよ。」
ゴムボールを持った少年が、ころんで血をながしているローラスケートの少年を見て口をあげて高らかに笑った。さっきまで泣いていた、ふたつの痛みを一度にうけた少年が、笑ったゴムボールの少年ににとびかかって、そのままポカポカ、大げんかになってしまった。ゴムボールの少年は、余程おかしかったのか、まだ笑っているのだ。
チョビはゆびをたてて、うすめをしてそれを見ていたが、それもすぐやめた。
「しかし、最近どうかね、サ。どうだい、なにかあったかい?なにか変わったことは起こったか?」
「どうもこうもないよ、だっていつもあんたとわたくしはくっついて一緒にいるじゃないか。どうもこうも、あるわけがないじゃないか。あれだけくっついてて、別のなにかおこるってのか?わたくしにはわからないね。」
チョビはどこから取り出したのか、ちいさいサテンの布をちらちらさせて、ともだちにいった。顔は口をあけ笑っていた。
「ヤーヤー。そんなこともないんだよ。サ。あたしってのは、サ、あんたが寝ているあいだに、そのナントイウカ、かっぱつにかつどうしてるんだから。サ」
にがにがしくもともだちはチョビをみやった。グラウンドでははらを殴られたゴムボールの少年がふっとんでいる。
「うそだ」
ベンチにたばこをもみ消すともだち。
「ほんとだよ。最近はよく夜中にギーたちの店にいくんだから。ほんとだぜ。」 ローラースケートの少年はたおれたゴムボールの少年の両腕を両足でおさえて、ローラースケートの柄のぶぶんでかれをぶん殴った。チョビがギーの店に行くこと。
「それはうそだ。うそだ。」
それはうそだ。ギーたちの店、ギーが持つ店、ギーがよく行く店、なんてものはない。だいたい、ギーたち、なんていうのが、うそくさい、
チョビは騙されているんだ、と思いながらともだちは、ショールをかけなおして、ジュースのふたをキシリ、とねじった。
「ああ、あの少年たち、ついに警察のごやっかいになったよ。ばかなんだ。ほんとうにばかなんだな。あたまが。あの少年たちも。ついに警察がくるまで喧嘩することをやめようとしなかったんだもの。ずっとけんかして。けんかばかりをして、ああいいうのは一生を喧嘩としてすごすんだよ。ばかなやつらなんだ。
ひとがあらそうのっていうのは、みにくいね。そうおもわない?サ。ちをながして、どじでさ。ばかだとおもわない?。わたしはそうおもうね。それをうつくしいなんていうことをいうひとがいる。よくよく心得るべきだ。
それはないよ。おおなしだよ。
子供がさ、かげんをしって喧嘩するってあれ、うそだよ。おおうそだよ、そんなの」
子供って、あんただって、かわったもんじゃないだろうに。ともだちはまたショールをなおしてから思って、今度はふたつめの、こんどはさくら入りパンをかじった、風がほこりをはこんできて、口のなかが少しジャリジャリした。
警官がローラースケートの少年の片腕を持ち上げて、鼻血を出しているそれを拭いた。チョビはいつもの写真をとるふうなそぶりをみせて、わきを見ずいってみせる。
「ああ、ああ、ああ。ごらんよあの出血とどろまみれをさ。あれじゃあいい男もだいなしだよ。みにくい!じつにみにくい!はなから血をだして。もったいないねえ。つくづくもったいないよ!」
公園ではもっと小さな子供たちが、りかいできないふうな遊びをはじめて大笑いをしていた。じゃんけんで負けた(あるいは勝った)一人の少年(あるいは少女)にみなが一枚づつ自分のジャンパーを着せてゆく。着せられたのがもう年長のもののジャンパーも着せられないぐらいの枚数(だいたい九枚)をかぶったときには、もうみんな大笑いしているのだけれど笑いながら真ん中の一人のやつがふらふらになって倒れる、たおれても太っているので痛みはない。子供のひとりがギーといって指差す。こんどは、もう一枚(なかには下着をぬぐもの、までいる)着ている服をかぶせる・・・。
ふたりはどっちということもなく立ち上がって、たべのこりなんかをごみばこにすてた。寒いのに天気はよくて、雲ひとつみつからなかった。
____________________
それから、ゆうがた。二人は小さなドーナツ盤のレコードを古道具屋から一枚、どれでもいいから適当に拝借して、ともだちのアパートでならす。
曲はロックならどうでもよかった。どういうわけかともだちのレコードプレイヤーは、ある一定の時間がすぎると回転が異常にあがって、曲にならなくなる。それを聞いて二人は顔をゆがめて、そのうちきぶんがよくなったところで、ロックのドラムのリズムで踊りだすのだ。コンコン、カタカタ。小さなスピーカーからはそんな音がなる。
レコードはさらに回転をあげて、小さいスピーカーからはポコポコと小さい音がでている。もう曲もあまり聴いていない様子。二人はおどって、その大きいおとはアパートの床をつたって、ドンドンドン、おんぼろアパートの入り口のポストのくちがバクバクゆれる。
ドンドンドン
チョビは小さいからだをゆすって踊る。ドンバタバタ。ともだちもクルクル、輪を描くように踊った。よそをむいて首をふる。またに手をつないでおどる。ふたりはなかよしだ。
カンカンカン。
上のへやの、生物の研究をしている紳士が床をたたく。きみたちうるさいという意味だ。チョビは首をよこにゆらして、ときどきピョン、とジャンプする。ピョンと飛んでも、落下するときの音はドシン。
ドンドン トントン カタカタ
ロックのおどりは雨漏りのようにはじめぽたぽた、ぽたぽたとすすんでゆく、その音はだんだんと大きくなっていって、しまいには大洪水になって、アパートじゅうをゆらすまでの激震となる。
回転するチョビの右手とともだちの左手がぶつかってぺちんといっておとがなくなる。くるりと一回転したぎゃくの手がこんどはばちんといって、思い切り衝突して、ふたりの手はまっかになる。このときにすこしともだちの顔がゆがんで、あかくなる。かいてんのスピードもいきおいもどんどんはやくなる。クライマックスはもくぜんだ。こんどはぐるぐるうでをいとまきにしてまわす。むこうずねをおたがいくっつけあわせて、スピードはぐんぐんはやくなる。
音がうるさいのにがまんしていた下の部屋の奥さんがどなった。
「なにやってんだいあんたたち!うるさいよ!いいかげんにしないか。いったい今なんじだとおもってんだい?このバカども!いいかげんにしないか。このバカども。このバカども・・・」
ともだちはその声をきいておもわずにが笑いをもらした。チョビはまじめになって、いつもの、何が起こっても平気、というつらがまえをした。
「このばかども、このばかども、このおおばかども!うるさい音ばかりたてて、わたしとこどもたちのすいみんをじゃまするんじゃあないよ!とっととやめるか、そのばで死ぬか、よそへひっこしてそのへたなダンス教室をするんだね、うるさいんだよ、このあばずれたちが!」
二人を傷つけるつもりの悪口はとどかなくて、二人はまだまだ踊り続けるつもりで、こんなことが夜二時すぎまでつづいて、おそい晩ごはんをたべて、ふたりのいちにちがおわる。
4
さて、ギーだ。ギーの話をしよう。
ギーはゆうめいなおとこだ。ちょっとでもテレビや、ラジオのスイッチをひねってみたまえ。そこにはなんびゃくものギーのにせものがいる。
今ある既存のスタイルはギーがほとんどつくった。ほとんどギーだ。ギーのこうせきははかりしれない。いろいろな古代の財宝をもたらす義賊のようなものだった。ギーのにせものも、だからかたみのせまいおもいをせず、ギーのスタイルをまねた。ギーもそのことについて思うところはなかった。とうぜん富や、名声はおのずとギーに溜まった。ギーの言葉はたいへん影響力があって、総理大臣や王様も、そのはつげんには一目をおいていたほどだった。
ギーはチョビのあこがれの人だ。たまたま、二人が仕事で、人間が住むような、入り口には立派な観葉しょくぶつのある住宅街に行ったときに、チョビが信号のコンデンサーに貼られていたギーのビラを手に入れた。そこにはギーと、ギーらしきものが載っていた。
それを見てそれからチョビはギーにぞっこんになってしまった。そうすると、生活のサイクルが、ねてもさめてもギーになった。ああ、ギー。と息つくときにはいう。いとしのギー。それでいちいち思い出すとしゃっくりのように動きがとまるのだ。
その状態たるや、心臓はどきどきとして(しかたがないのでともだちはうちわであおいだり、水を汲んできてやらなければならなかった。ときには朝食のしたくも必要だった)、顔が際限なくゆるんだ。
そういうとき、よけいなことすらしないような、まったくつかいみちのないチョビはかわいかった。二三日なんのつかいものにならないけど、ともだちはそういうチョビのことをなによりかわいいとおもったし、なかには抱きしめてやりたい、と思うときだってあった。
はじめのころは、そうだ、はじめのころ彼女がチョビのともだちをはじめてまもないころは、チョビのともだちはチョビをよく女の子がするようにかわいがったものだ。よくあたまをなでてやり、くちうつしかなんかで水をのませてあげたり、お金があるときはごはんをごちそうしたり、そうでないときはおべんとうのおかずを半分あげたり、いろいろサービスをした。
「ギー」
チョビのうなりごえ。
こいをすることは自由だ。ましてギーなど。ギーを相手にこいをするのは、自由だというよりもそれがギーの仕事の三分の一ないしは五分の三だったのだから。
でもチョビはすごくみにくい顔をしていた。そりゃ、だれもがこいをしていいかもしれないがな、とともだちは思う。
化粧をとるとチョビはつぶれた食べ物のようで(ともだちがいうには)こんな酷い顔本人をふくめて誰も好きにならない、といったふうだった。肌は(ともだちがいうには)みそを塗ったようにでこぼこのときがあった。
それでも(ともだちがいうには)さえない、へんな男がチョビをちやほやしたりはやしたりした。そいつらは誤解してんだ、とともだちはよく思った。あんな男どもよりも、自分のダーリンのほうがいい男だ。ともっと若いごろには思うときもあった。いまにしたら、それも恥ずかしいことだけれど。とにかく、この件にかんしては、いつもと同じようにこうりょ外のことだった。ギーなんていうのは、もう雲の上のそんざいだからだ。
5
ブルースたちがまだちまたを駆けめぐっていた時期だった。世の中は経済的に不況で、どこかの王国の国王や、大統領や、総理大臣が暗殺されて、戦争はまだ終わることを知らない時期だった。
いまやブルースは前時代的なしろもので、黄金時代のものとはほど遠いなにかだった。しかしギーを生んだのも、そのオーゴンキのブルースの土壌があったからだった。なんにんものチョビみたいな子が、でっかいおしりをかくすようにしても、はちきれるようなホットパンツをはいて、ブルースのおとこたちや、女の子たちとチュウをしたり、むねをもちあげたり、もっともっといやらしいことを何回もして、化粧などして金をかせぎ土壌を築きあげていた頃のことだった。ブルースはノリにノリまくっていた。
ブルースとギーはそういう時代に育った。ギーがブルースの井戸から、ふしぎなせいめいのみずを、でかいバッタでもつかまえるみたいにくばってあるくのか、そうそうおそいことでもなかった。お金はほどなく貯まった。
ブルースとギーはそういう時代に育ったから、チョビみたいななんまんにんものギー好きたちは、そういう時期そういう時代を追いかけるようなかっこうをしていた。
チョビがこないだ「ギーの店」といったのはそういう時期の雰囲気を持っている三十件ある建物のうちのひとつだった。
その時代、ブルースの時代ならブルースの時代をおいかけること。それはそれでとても大きなお金がうごいて、立派なきかい、立派なふくそう、背広をきた立派なひとびとの生活をうるおす立派なしごとだ。
それでどちらかというと、汚いかっこうをしてうるおっていないチョビとともだちが、仕事のかえりにその「ギーの店」(たぶんにせものだろう)にきて酒をのんでいる。
「ヤア。いいね、ヤア。ヤア。いつきてもサ。ここ。フウ。いいねえ。ホウ。ね、そうおもわないか?」
「うん。そうだねチョビ、だからってあまりのみすぎるんじゃないよ。あんたはさ、お酒にお強いか、お弱いかっていったら、ずのうとおなじくお弱いほうなんだからさ。わかってんの」
「クゥ。なんだかいきなりくちうるさいこというなよ。くやしげな。あんたおねえちゃんみたいじゃないの。フウ」
店はこの街で一番有名な服のメーカーのディスプレイがある二件となりの、模型店の地下にある。店にはいろいろな装飾をした、飛行士やらアラビアの王様などの模型が飾られている。
店のなかは暗くて相手のかおはよくは見えない。ときどき、マッチをつけたその顔がぼう、ときみわるくうつるのみだ。
マッチ遊びをしていたペルシアの服装をした兄さんが、それにも飽きて焼いた指輪で店のかべに傷をつけている。しばらくするとボーイがとめにはいる。
「おきゃくさん、こまりますよ」
(とかなんとかいってるんだろう)
「うるさいね」
とかなんとかいってるんだろう。音がじゃまで何をはなしているのかは分からない。
ともだちがひまをもてあまして、ピアノ線でつり下げられていた初期の飛行機の模型をくるくると回す。すると飛行機の尾翼のいちまいがひとつおちて、ともだちがにがわらいをもらす。
チョビはだるそうに奏でられている音楽にしずんでゆく。うなだれて頭をななめにふる。だらしない、かおだ。
店の中では変則的ブルースが流れていた。とても近代的な、新しいブルースだった。新しい時代のブルース。ブルース。
チョビも、ともだちも、新旧を問わずブルースというものが大嫌いだった。古典的ブルース、抽象的ブルース。へどがでる。芸術的ブルース、装飾的ブルース。荘厳なブルース。へどがでる、というきたないことばがブルースについてならば平気で口をついででてくる。
ブルースなんて大嫌い
ブルースなんてしんじまえ
ブルースなんてバカヤロ
ワッハッハー ワッハッハー
ブルースなんて陽気だよ
ブルースなんて楽しみだ
ブルースなんておかしいなあ
ワッハッハーワオワオワー
ブルースしねしねブルーゥース
それがまた、巷に流布してべつのブルースにる。
ブルースはブルースを生むようにできていた。こんなふうだ。
東のそらでブルースが死んじまった。ワアワアワア。ブルースがおちてくる。腐ったブルース。おもろいブルース。ワアワアワア。その腐ったブルースはにせものだ。ワアワアワア。ブルースはおまえさ。死んだボーリングピンのブルース。そんなものはにせものだ。ブルースはおれさ。ブルース、ブルース、ブルース・・・・・・
ブルース
チョビがウィスキーのダブルをおかわりする。
「ハァ。ほんとに、こういう音楽にはあきあきだよ。フウ。あきたあきたあきた。もうひとつつけたらばあきたよ。そうおもわない?。サ。あんたのふくそうと同じ。まいにちまいにち、なんまんかい何十憶かいおんなじことばかりで。クゥー、ちきしょうめビ・バップは流れないのか」
ボーイさんにもらった氷を、歯のはじでがちがりかじっていたともだちは、うつむきかげんになってしまい、ズルズルとチリソースをすするチョビにみみうちする。
「おい。チョビ。おい、チョビ。なにがギーみたいな店だよ。チョビ。あんたこのままじゃおおうそつきでおしまいだよ。チョビ。このままじゃ、あたしとっても暗い気持ちでかえるみたいだ。どうしてくれんの。金かえせ。このくちわる。」
くちをまっかにしたチョビが上のランプをながめながらなげく。
「そんなけちなこというなよ。いいみせじゃないか。みみをふさいでいてよ。お酒おいしいし」
たとえばブルース的に文章をつづるとこんなふうだ。
あさ、ブルースが、ブルースとブルースしていた。ああ、そうさブルースがもってたブルースっぽいやつだよ。とってもブルース。どうしょもないブルースだったよ。でっかいブルースをブルースしてました。それでブルースたちは、ブルース的ブルースを行いました「なんたってブルースなんか」。それでブルースたちはさらにブルースを手に入れて、ブルースになった、それでブルースになった、それがブルースになった・・・・。
にさんにんのカップルが音楽にあわせて、手でわをつくってそれをまわすようにして踊る。肩はだんだんと下にしずんでゆくようで、からだをつけあったり離したりする。いやらしいおどりだ。
それをみてチョビに似た老人がひたいに手をあててこれは見ていられない、これは俺のせいなのか、誰がわるいわけでもないのに、というそぶりをする。チョビはとなりのにんげんにもらった鉛筆でなにやらわけのわからぬ計算をはじめた。ブルースはまだつづいていた。ブルースが流れたためにとある男は幸せにしてやれない故郷の母親のことを思いだし、泣いていた。いまでもその母親は立派になってさとがえりをする自分を信じながら待っているからというのだ。となりではしゅうだんで農場を経営する恋人どうしたちが抱き合ってすまたをしている。ブルースは農場を経営する恋人たちをつつみまわす。
ブルース。曖昧でいやらしいもの。みわけのつかないもの。だからふたりはブルースがきらいだった。
だからふたりのうたいたいうたはたいていブルースじゃなかった。もっと幸せな、明確なこいのうただった。よくあるポップス。こいの歌。こいは憎しみと区別のできる、はっきりとしたなにものかだ、ブルースみたいにあいまいじゃない、というのが二人のじろんだった。
「おきゃくさん、こんどかべに傷をつけたらべんしょうしてもらいますからね」
男が伝票を書いている。ブルースがはやくおわらないだろうか。ブルースが、はやくおわらないかなあ。
はやくおわらないかなあ。
6
でもまさか本当に来るとはおもってもみなかったのだ。
ギーが登場したのはその日五分くらいで、しゃべったのをいれて六分三十二秒くらいだった。いつでも冷静なともだちが、どぎまぎとして、ジュースののみかたの順序を間違えたくらいだった。チョビは麦茶とウィスキーを間違えてのどがかわくためにがぶのみしてほんとうに目をぐるぐるまわした。「ゆうしてっせんはじまっていらいの!」とチョビは何度もくりかえし声をからしていた。
店ではその手のチョビたちと同じような客が同じような理由でおおざけを飲んでしまって、ビールの配送会社と帰りのタクシーがこんらんし、いくらかのそんがいをこうむったという。
なかには泥酔しているために乗車拒否されるものもいた。もちろん、チョビもそのなかの一人だった。
(まぐれとはいえ)その日は記録的な、伝説的な夜だったのだ。
7
かえりみち、今日のかえりみちはチョビはよっぱらってしまっていて何も言えない。
いつもの月が出ている限り。今日は良い日だ、何もいうまい。げろを吐くばかり。いつもの坂はつらいので今日は帰らない。うらの、じりじりとした斜面の通りを歩いていく。つながらないように歩いていく。はがれないように二人はあるいてゆく。ごみばこに足をつっこんで、歩いていく。
「ばかチョビれ。そんらり飲むな。そんれ、さわぐなバカ」
よそ行きの、黒いシルクのスカートをまくしあげて、ふとももまで片足をごみばこに入れているチョビが、信じられずに、つき放されたようにともだちを見る。
「ばかばかいうなよー、あたしあ、こいでもあんたをすくっちゃってんだよう。あんたを。ばかいうなよなー。すくっちゃってんだ。のい!れいをいうんだー、サ」
おどろいたチョビをすぐむかえにいってともだちがむねにいだく。
「わかってる、わかってんだよチョビ、あたしのことを、今すくってくれてたんだね、わたしのかわいいチョビや。こっちおいで。チョビや。チョビ」
「マーマ!」
仕事で恐ろしい目にあうときと、酔ったときには、ふたりはだきあってじょうねつてきチュウをする。マーマ。(いないわけでもないのに)チョビがマーマを思いなきだす。じょうねつてきチュウ。
チュウ、チュウ、にかいでは飽き足らない。情熱的なチュウをする。ともだちがちからいっぱい抱きしめて、その強さでチョビの肺はぽきぽきとおとがなって、チョビはせつなくなってともだちのむねのなかで泣いてしまうほどだ。
よくよく悪口をいいながら、二人は強く抱き合ってチュウをする。悪口をいって、だいきらいなかんじでも、二人はチュウをすることに夢中だ。キスをしながら、クモのようにしたともだちの手がチョビのせなかをつかまえる。たじたじになって、チョビはくつのかたあしをおとす。
キスはまだつづいている。
フウフウ。つかれたチョビがくちづけする歯のあいだからよこに息をもらす。ともだちは、ちょっと目をあけて、どこを見るかといえば、汗をかいたおでこでそらをみる。
街の天上はすみわたっていて、おつきさまがまあるくわをつくっている。おつきさまが見守って下さっているようだとチョビが言った。今日のこの日のことをわすれないでいましょうね、とともだちが言った。ぎーだ。とチョビがこたえた。
ぎーのいるまちぎーのつくったまちぎーのそだてたせかい。おおげさだが、チョビはもうそういうかたちでよのなかを見るようになっていた。ギーギーギー。クモのような手がちょびのせなかをたじたじにする。今日のこの日をわすれないでいましょうね。ギュッとつかんで、関節がポキポキおとをたてる。そらをみれば月だ。いくらかひびがはいっている。
すばらしい!チョビが感嘆の声をだす。ここは大都市くうかんですぞ!
なによお、もう!よっている友達がぶつくさもんくをいってチョビのにのうでをつねる。いやねえ、もう。ぶちこわし!チョビはねむっていた。
「ギー」
ぐずぐずとかべぎわで沈んでゆくチョビがいびきのようにぎいと言う。ともだちも、ねいきのようにキーと小さな声でいう。路地裏でぞうきんのようになっている二人を邪魔するものはいなかった。ぞうきん以下の存在のふたり。
チョビは言葉にならないような夢をみて、思い切りねがえりをうって、それが縦置きにしてあったローラーカーを倒した。倒したローラーカーは反対側にあった水道管(らしきもの)に直撃。直撃したパイプから小さな五ミリほどの穴が空いて、そこからぽたぽた、眠っているチョビのひたいに水が垂れる。いちどひずんだパイプからまた別の水もれあながあいて、今度はジャー、と一定の間隔でひっくりかえったような水がながれる。ジャー、どしん。二秒間隔のその水が、運悪くチョビのせなかの中に入る。
「ギャー。チベタイ!しとごろし!」
暴漢が襲ってきたのだとおもったともだちは、とっさにかばんに隠していたナイフをとりだそうとして、ぬかるみにつかまってすべってひざをすりむく。すでにあばれまわって二三度も泥につかったチョビが、ゾンビーのようにみにくくあたりをふらついて、ベチンと今度は顔面をうつように倒れた。ぞうきん以下のふたり。
「どこどこどこどこ?」
「ブクブクブク(なんでもない)」
みじめだな。でもそのみじめな顔を上からふってきた水がながしてくれる。今日という日をわすれないでいましょう。あらいながしてくれるそばから、足下でどろみずになってくつの下をどろどろにする。よごれた顔はいつかきれいになった。でもみじめさはのこるのだ。みじめだなあ。ギーよ。
チョビはころんですねをけずってしまい、犬みたいに舌を出していて、またころんで、口をかんでしまった。しばらくその場にへたりこんで口をつぐんでいたチョビが
「いやあなあじ!」
という。チョビはもう立ち上がることができなかった。
8
「ねえ、サ」
「なんだよ、うるさいな。いちいちあんたのからだはおもたいんだよ。すねをけずったからってね、あるけなくなるんじゃないよ。このトンマ」
「まあそういうなよ。ところでだ。ところでだよ、ねえ。ところでたとえば、このよのなかのひとはさ、なんでみんなこうもふこうもちなんだろうね。そうおもわない、サ。」
「あんたほどの目方をもったふこう人はいないよ。それに、あんたがいうほどみんな、ふこうじゃないよ」
指をさすチョビ。眼前には月がある。
「まちをみてごらんよ、ギイ」
「ギイなんてよびかたするなよな!」
「いいじゃない!」
「ギーにあえたからって、調子にのるなよ。ギーにあえたからって、調子にのるなよ。そういうのは悪いことがおこるぜ、調子にのるなチョビ。そういうことは悪いことだぜ。おい」
「まあ迷信ぶかい!。ねえ!まちをみてごらんよ、そしたら、すぐわかるぜ、そんなこた。このあいだ、あんたの家のアパートから、まちをごらんじたんだよ、あたし。それはね、景色がいいけれど、笑いがおがあるけれど、その裏には、暖かい暖炉の下に、しみがあるみたいにさ、ふこうがへばりついてるんだよ。きたなく。
たぶん、そのことと、みんな大切なものがひとつぐらいしかないってことと、関係があるってだって、あたしはふんだんだよ。ねえ、そうおもわない?」口をつぐむともだち。
「!」
「だって、おまえ、ゴージャスなことなんて、そういうこと考えろってったってさ、ひとつぐらいしかうかばないだろ。このよでただひとつのほんとうに良いこと。こうふくなこと、ゆうふくなことなんて、そんなひとつぐらいしかありゃしないじゃないの。ほんとうのこと、家族がいて健康なこと、じゃあ、家族がいて不健康はもうふこうかい?ふこうだね。」
「チョビ、あんたにしちゃ、ずいぶんと学がおありだね」
「じゃあ、ふこうは、そのだいじなひとつがないことなのさ。そうやって、明るい場所ができる暗いところもできて、うらおもてができちまう。いやあな。だから、こうふくなすがたをしたやつらは、みんなあたしにはふこうだって、わたしはこうおもうね。」
もうろうとした意識のなかで、ともだちはむねをはって座っているようなチョビのすがたのことを考える。
「どうだい?、あたしのともだち」
「そりゃ、少しは思うよ。そういうこと。そういういろいろなこと。不幸だってこと。ゴージャスなこと、影みたいにあるしみのこと。そういうこと・・・」
ともだちはまどろみながら、落ちそうになっているチョビの足をかかえこんでもとにもどす。
「だろ。そしたらさ、わたしが生まれてきたっていみは、そういう不幸をなくすてつだいをすることじゃないかっておもうんだよ。ギーみたいに」
「そんなたいそうなことが、あんたにできるもんか」
「そんなこた、やってみなけりゃわかんないぜ」
「そんなこた、やってみなくたってわかるよ。一目瞭然さ。だったら、まず、その濡れそぼってぶよぶよで、でぶった腹をどけて、あたしのせなかからおりて、自分の足で立って、笑顔をふりまいて、歌いながらも陽気なあしどりであるいてみせなよ。チョビ。そんで片手、片足でもってピョンピョンとはねてさ、あそこの自動販売機でわたしに気前よくでもリンゴジュースをおごんな、あんた。いまのチョビをうしろからみたら、ぶざまなもんだぜ。きょうだい、血をだして、しみるしみるガーゼでふいてないてさ。」
チョビの顔が少し、つちけいろになる。
「アーアーそうじゃないんだってワカッテナイナア!。そんなちいさいことじゃないんだよ。サはほんとに、ばかだなあ
ワカラズヤだし。」
ムッとしてチョビのともだちは口をつぐんだ。口のわきから声をもらす。
「わかりゃしないよ。あたしは、あんたみたいなやりかたが嫌いだよ。どっちにしろ嫌いなのさ。へばったふりばっかりして。あんただって、やりゃあできるんだって、わたしおもうよ。見るばかり、見せるばかりで、ときどき、バカじゃないかって、本気でそう思うぜ。トンチキ」
「そりゃあそうなんだ。おれもそうおもってるんだ。このうずらあたま」
「じゃ、あるきな。ほら」
「オットット。」
「あるきなよ、ほら」
「オットット。」
あるきなよ、なかなか降りないね、こいつ。ほら。オットット。オットット・・・
チョビとそのともだちは五番街の本通りの、ゴムぐつが目印の小さな運送店で働いている。 |